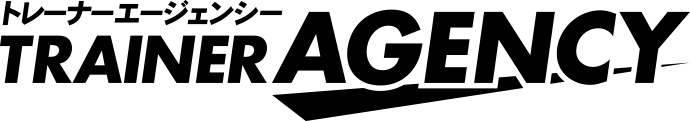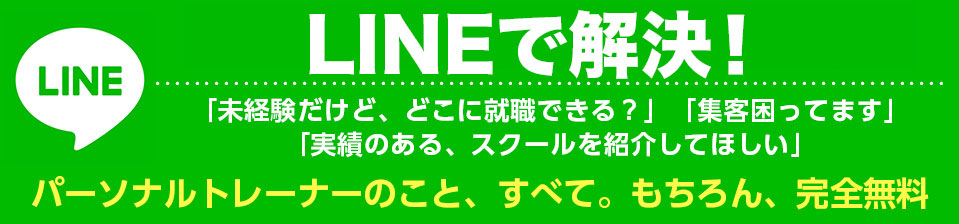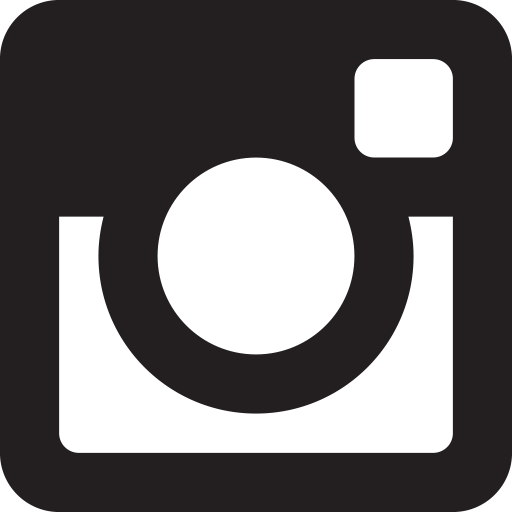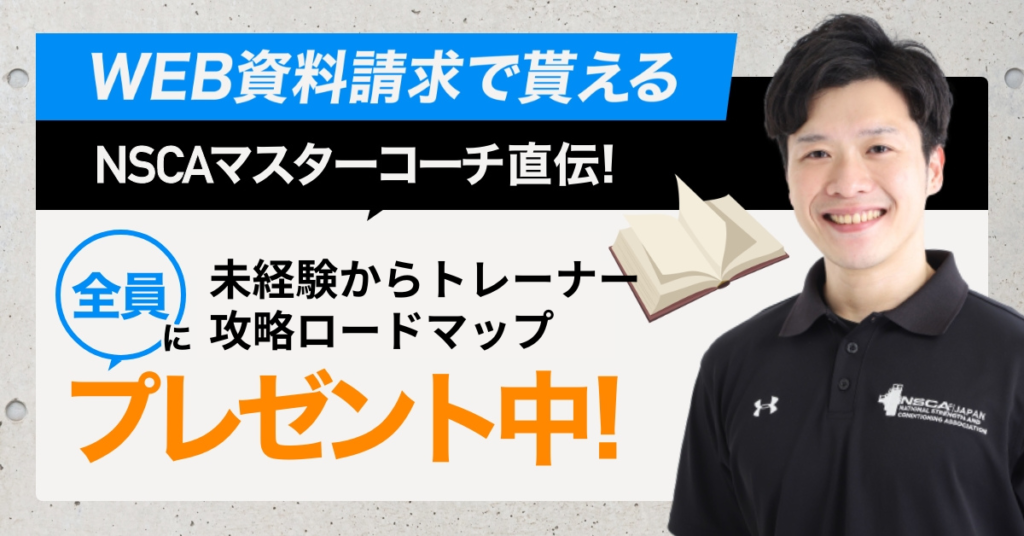スポーツトレーナーに向いてる人の特徴とは?やめとけと言われる理由も解説
 最近、スポーツジムやフィットネスジムの人気が高まっており、今スポーツジムの会員数が伸び続けています。
最近、スポーツジムやフィットネスジムの人気が高まっており、今スポーツジムの会員数が伸び続けています。
こうした背景を受けて、テレビやYouTubeなどでスポーツジムのコマーシャルを頻繁に見たり、街中で新しいジムが続々とオープンしているのを目にしたりしている人も多いのではないでしょうか。
その一方で、「お客様としてではなく、スポーツトレーナーとしてスポーツジムで働いてみたい」「スポーツをしているお客様をサポートするスポーツトレーナーになりたい」という人も急激に増えています。
しかし、いざスポーツトレーナーを目指すとなると、
「そもそも自分がスポーツトレーナーに向いているかが分からない」
「インターネットなどで『スポーツトレーナーはやめとけ』というのを見たことがあるため、スポーツトレーナーへの一歩が踏み出せないでいる」
「スポーツトレーナーになるのに取るべき資格がわからない」
などの不安や悩みが出てきてしまうという声も実際に多いです。
そこで今回の記事では、スポーツトレーナーに向いている人の特徴や「やめとけ」と言われている理由、スポーツトレーナーを目指す方におすすめの資格などについて詳しく解説していきます。
スポーツトレーナーになりたいけれど、なんとなくモヤモヤしてしまっている方は、ぜひこの記事を読んでスッキリしてください。
スポーツトレーナーとは?
まず最初に、スポーツトレーナーについて詳しく探っていきましょう。
本項ではスポーツトレーナーの
・役割
・種類
について以下で詳しく説明します。
スポーツトレーナーの役割
スポーツトレーナーの役割は、スポーツをしている人のパフォーマンス向上や健康維持、ケガの予防や回復などをサポートすることです。
スポーツトレーナーは、プロのスポーツ選手から一般の人まで幅広い層の人を対象にしてサポートします。
スポーツトレーナーの具体的な仕事内容は以下の通りです。
・お客様の目的を効率的に達成させるため、トレーニングメニューを作成し、実施する
・コンディショニングを指導し、心身の状態を整えることでパフォーマンスを向上を目指す
・リハビリテーションの補助をすることで回復をサポートする
・ケガを予防したり、ケガした場合には応急処置をしたりする
・栄養指導やライフスタイルについてのアドバイスを実施し、お客様の健康維持に努める
など
スポーツトレーナーの種類
スポーツトレーナーには、役割によって様々な種類があります。
本項では、スポーツトレーナーの種類である
・フィットネストレーナー
・コンディショニングトレーナー
・ストレングストレーナー
・リハビリ系トレーナー
の4つの職種について以下で詳しく説明します。
フィットネストレーナー
フィットネストレーナーは、フィットネスクラブやスポーツジムでお客様に対してトレーニングや運動、栄養、生活指導などを行うトレーナーです。
フィットネストレーナーの多くは、パーソナルトレーナーとして働いています。フィットネストレーナーよりも、パーソナルトレーナーの方が聞き馴染みがあるという人もいるかもしれません。
パーソナルトレーナーは、トレーニングをしているお客様に対して、一人ひとりに合ったトレーニングプログラムを作成し、マンツーマンでトレーニング指導や栄養・生活についてのアドバイスなどを行います。お客様が効果的に自分の目標を達成できるようサポートするのが仕事です。
コンディショニングトレーナー
コンディショニングトレーナーは、プロのアスリートや一般の人の体調管理や心身のバランスの調整のための指導を行います。
コンディショニングトレーナーの具体的な主な仕事は、以下の通りです。
・試合や練習の前後でコンデションを整え、競技のパフォーマンスを最大限に引き出す
・筋肉の補強や緩和、柔軟性の維持をすることでケガを予防したり、身体の機能の回復を促したりする
・ストレッチやマッサージをすることで疲労回復をサポートする
など
ストレングストレーナー
ストレングストレーナーは、プロのアスリートや一般の人に対して筋肉や体力、持久力などの筋力機能を強化させ、最高のパフォーマンスを発揮できる身体を作るサポートをします。
ストレングストレーナーの具体的な主な仕事は以下の通りです。
・トレーニングメニューを作成し、指導する
・ケガの予防を目的としたプログラムを組む
・食事指導・メンタルケア・ドーピング教育などを行う
など
リハビリ系トレーナー
リハビリ系トレーナーは、ケガや事故、病気などが原因で運動機能が下がってしまった人に対して、運動機能の回復をサポートするトレーナーです。
リハビリ系トレーナーの中には国家資格である、
・理学療法士
・柔道整復師
・鍼灸師
などが含まれます。
リハビリ系トレーナーの具体的な主な仕事は次の通りです。
・効果的なリハビリテーションプログラムを提供する
・リハビリテーションの指導やサポートをする
・栄養指導・メンタルケア・ケガの対処法指導を行う
など
トレーナーエージェンシーでは、
・トレーナーとして必要な素養
・具体的なトレーナーの働き方
・おすすめの資格
・トレーナー資格試験の力試し模擬問題
・うまく行く人/いかない人の違い
などをまとめた「【完全版】未経験からトレーナーになるための攻略ガイドブック」を”無料でプレゼント“しております。(内容の一部を先んじて見せちゃいます!)
下記ボタンからダウンロードできますので、ぜひご確認いただいた上で、ご自身の学習にお役立てください。
スポーツトレーナーに向いてる人の特徴とは?
目指すべきスポーツトレーナーの種類は分かっても、そもそも自分自身がスポーツトレーナーに向いているのか不安な人もいると思います
そこで本項では、スポーツトレーナーに向いている人の特徴を解説していきます。
実際、スポーツトレーナーに向いている人の特徴は、
・コミュニケーションが好きであること
・向上心があり継続的に学ぶ意欲があること
・柔軟な働き方ができること
・物事を論理的に考えることができること
・他者のために尽くすことができること
・教えたり褒めることができること
の6点が挙げられます。それぞれについて以下で詳しく説明します。
コミュニケーションが好きであること
スポーツトレーナーに向いている人の特徴の1つ目は、コミュニケーションが好きであることです。
コミュニケーションが好きであることは、スポーツトレーナーに向いている人の特徴というより、スポーツトレーナーに必要不可欠な特徴と言っても過言ではありません。
スポーツトレーナーは、お客様相手の仕事のため、お客様と信頼関係を築くことが非常に重要になりますが、信頼関係の構築に良いコミュニケーションは欠かせません。
また、お客様が目標を達成するのに重要な要素の1つも、スポーツトレーナーとのコミュニケーションといえます。
目標を達成するためには質の良いトレーニングをすることが大切ですが、一番大切なのはトレーニングを継続することです。しかし、トレーニングはお客様に負荷をかけて行うため、挫折しそうになる人や実際に挫折してしまう人も少なくありません。
そのため、お客様を励ましてモチベーションを上げるスポーツトレーナーのコミュニケーション能力が必要になります。
さらに、スポーツトレーナーとのコミュニケーションをとる中で、お客様の食生活や過去のケガなどについて知ることができ、それが目標達成を阻む問題の解決策に繋がることもあります。
以上のことから、コミュニケーション能力はスポーツトレーナーに絶対に必要なスキルだということが分かるのではないでしょうか。
向上心があり継的に学ぶ意欲があること
向上心があり、継続的に学ぶ意欲がある人もスポーツトレーナーに向いています。
スポーツトレーナーは、お客様を指導する際にスポーツ医学や運動生理学などのスポーツに関わる知識や、ダイエットなどの美容についての知識などが必要になります。
スポーツトレーナーの資格を取る際などに、これらの知識について一通り学びますが、医学やスポーツ、美容に関する情報は日々進化し変わっているため、スポーツトレーナーになった後も持っている知識を常にアップデートする必要があります。
実際にスポーツトレーナーとして活躍している人は向上心や学習意欲があり、
・セミナーやワークショップなどへの参加
・オンライン講義の受講
・専門書や論文の購読
などをすることで知識のアップデートをしている人が少なくありません。
「お客様に新しい情報を与えたい」「新しい知識を身に付けることに喜びを感じる」などの気持ちがないと、スポーツトレーナーとして活躍することは難しいといえるでしょう。
柔軟な働き方ができること
チームに帯同するスポーツトレーナーを目指すなら、柔軟な働き方ができるスキルがあると良いかもしれません。
チームに帯同するスポーツトレーナーは、その収入だけでは生活費を賄えないことが多いからです。
日本は海外と違い、チームに帯同するスポーツトレーナーやスポーツ選手などが経済的に厳しい状態になることがよくあります。そのため、
・複数のチームとの契約
・パーソナルトレーナ
・インストラクター
・オンライントレーニングトレーナー
などをかけ持つことで、経済的な自立を目指す人も多いです。
チームに帯同するスポーツトレーナーは、副業や兼業を考えてパーソナルトレーナーやインストラクターとして働けるスキルも身に付けておくとよいでしょう。
物事を論理的に考えることができること
スポーツトレーナーに向いている人の特徴として、論理的思考ができることも挙げられます。
スポーツトレーナーは決まったマッサージやトレーニングをするのではなく、目の前にいるお客様の状態を見て、解剖学の知識などの論理的な視点や分析力を使いながらトレーニングメニューを作成することが必要です。
例えば、膝の痛みを訴えるお客様がいたとします。
素人的な考えの場合、論理的には考えずに膝の痛みに効果的とされる一般的なマッサージとトレーニングを提案してしまいますが、スポーツトレーナーは専門家として、論理的思考に基づいたマッサージやトレーニングを提案しなければなりません。
まず、お客様のバックグランドや生活習慣などを詳しく聞き、解剖学的な知識を使って痛みの原因を特定します。その後、痛みの原因に合わせたトレーニングメニューを作成していくことがスポーツトレーナーには求められます。
スポーツトレーナーには、原因を突き止める分析力とトレーニングメニューを作成する論理的思考が必要だということは覚えておいてください。
他者のために尽くすことができること
他者のために尽くすことができる人は、スポーツトレーナーに向いているといえるでしょう。
スポーツトレーナーの最重要課題はお客様の目標達成なので、自分のことよりもお客様のことを優先して考える姿勢がスポーツトレーナーには必要になります。
また、お客様を最優先するということは、お客様の立場に立って考えるということでもあります。
お客様が何を求めているのかを感じ取り、お客様が望んでいることを即座に提供できたり、それをトレーニングに活かしたりすることのできるスポーツトレーナーは、お客様から信頼されやすい傾向があります。
そのため、他者のために尽くすことができる人は、スポーツトレーナーとして成功する可能性が非常に高いです。
教えたり褒めることができること
最後にご紹介するスポーツトレーナーに向いている人の特徴は、お客様に教えたり褒めたりすることができることです。
前述のとおり、お客様はトレーニングをきついと感じることが多く、挫折してしまう人も中にはいます。また、なかなか結果が出ず悩んでしまうお客様もいるでしょう。
スポーツトレーナーには、成果が得られずつまづいているお客様に上手に教えたり、少しでもうまくいった時には全力で褒めてあげたりできる人が向いています。
上手に教えたり褒めたりすることで、お客様のモチベーションを保つことが期待できます。
モチベーションの維持は、お客様がトレーニングを継続する大きな理由になり、結果的に目標達成に繋がります。
スポーツトレーナーに向かない人の特徴とは?
ここまで、スポーツトレーナーに向いている人の特徴について見てきましたが、逆にスポーツトレーナーに向かない人の特徴が気になるという人もいるのではないでしょうか。
本項では、スポーツトレーナーに向かない人の特徴である、
・他社とのコミュニケーションが苦手なこと
・責任感がないこと
の2点について、以下で詳しく説明します。
他者とのコミュニケーションが苦手なこと
先程、スポーツトレーナーにはコミュニケーション能力が必要不可欠であることをお話ししたように、他者とのコミュニケーションが苦手な人は、スポーツトレーナーには向いていないといえます。
コミュニケーションが苦手であったり、コミュニケーションスキルがなかったりする人がスポーツトレーナーになると、次のようなことが起きる恐れがあります。
・お互いを理解することが難しく、お客様から信頼されない
・トレーニングがつまらなくなり、お客様のトレーニングへのモチベーションを下げてしまう
・コミュニケーション不足が原因で、お客様の求めているものが分からない・問題の解決策を導き出せない
など
以上のように、フィットネスクラブやスポーツジムでのスポーツトレーナーの仕事は、コミュニケーションなしでは成り立たないといえるため、コミュニケーションが苦手な人がスポーツトレーナーになるのは難しいでしょう。
ただし、スポーツトレーナーとしてのトレーニング動画の配信などで人気が出るなどすれば、コミュニケーションが苦手でも成功できる可能性はあります。
責任感がないこと
責任感がないことも、スポーツトレーナーに向かない人の特徴として挙げられます。
スポーツトレーナーはお客様の身体を取り扱う仕事なので、お客様の身体に責任を持ち安全にトレーニングを指導する義務があります。
また、責任感のないスポーツトレーナーは、お客様が目標達成するのを見届ける前に自分の都合でスポーツトレーナーを辞めてしまったりすることも考えられるでしょう。
ほとんどのお客様は、「せっかくトレーナーと一緒に頑張ってきたのだから、最後まで見届けてほしい」「目標を達成してトレーナーに褒めてもらいたい」と思っているはずです。
責任感がなく途中で仕事を放り出してしまうような人は、お客様をがっかりさせてしまう可能性が高いため、スポーツトレーナーには向いていません。
「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われる3つの理由
スポーツトレーナーになりたい人が増えている一方で、「スポーツトレーナーはやめとけ」という声もインターネット上などで見られます。
なぜそのようなネガティブな声があるのかその理由を探っていきましょう。
本項では、「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われる理由として考えられる、
・安定した働き方が難しいと思われている
・フィットネス業界の将来性がないと思われている
・年齢を重ねると働くことが難しいと思われている
の3つについて以下で詳しく説明します。
安定した働き方が難しいと思われている
「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われる1つ目の理由は、安定した働き方が難しいと思われていることが挙げられます。
これは全くの誤解です。
スポーツトレーナーとして働いている人の中には、フリーランスやジムの経営者として働いている人が沢山います。
フリーランスや経営者は、お客様や契約の数によってその時々で収入が違うため、安定した働き方が難しいというイメージがついてしまっているのかもしれません。
しかし、スポーツトレーナーの多くは、ジムや企業に雇用されて社員として働いています。
社員として働いているスポーツトレーナーは、経営者のように高収入は期待できないものの、普通のサラリーマンのような安定した働き方が可能です。
スポーツトレーナーは様々な働き方があり、それぞれに長所と短所があるためよく調べて自分に合う働き方を選んでください。
フィットネス業界の将来性がないと思われている
フィットネス業界の将来性がないと思われていることも、「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われる理由の1つです。
フィットネス業界の将来性は本当にないのでしょうか。
フィットネス業界の市場は今拡大し続けていて、今後の超高齢化社会の到来や人々の健康志向、ダイエットブーム、人生100年時代に向けての健康維持などを考えると今後も拡大傾向にあると考えられているのが実際のところです。
また、スポーツ庁のスポーツの成長産業化のページを見ると、「スポーツ市場を拡大し、その収益をスポーツ環境の改善に還元し、スポーツ参画人口の拡大につなげるという好循環を生み出すことにより、スポーツ市場規模5.5兆円を2025年までに15兆円に拡大することを目指します。」と明記されていて、国がスポーツ産業を後押ししていることも分かります。
以上のことからフィットネス業界の将来性は、ないどころかかなりあると言うことができます。
将来性がないというイメージが広がってしまったのは、おそらく新型コロナウイルスの影響で一時的にスポーツジムの需要が減少してしまったためでしょう。現在は行動制限がなくなったこともあり、スポーツジムの市場は回復しています。
したがって、一時期のイメージにとらわれず、実際の市場動向を見ることが大切です。
年齢を重ねると働くことが難しいと思われている
「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われる理由として、年齢を重ねると働くことが難しいと思われていることも挙げられます。
実際に高齢になりお客様と一緒に身体を動かすことが難しくなった時に、パーソナルトレーナーの仕事を続けられないのではないか、と不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
スポーツトレーナーの雇用は、若い人の方が有利なことは確かにあります。しかし、高齢になっても健康であれば仕事を続けていくことは可能です。
最近、人生100年時代を見据えて、多くの高齢のお客様がジムに通うようになりました。
ご高齢のお客様の中には、若いトレーナーよりも同じ年代のトレーナーを希望する人もいます。
また、高齢のトレーナーが今までの経験を活かしてトレーナーの育成やジムの経営をすることで、今まで以上の成功を手にする例もあります。
以上のように、高齢のスポーツトレーナーだからこそ必要とされたり、成功できたりする場合も多々あるのです。
スポーツトレーナーがおすすめな職業である3つの理由
「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われる理由と、その多くが誤解であることを説明してきました。
今スポーツトレーナーは、おすすめの職業の中の1つです。
本項では、スポーツトレーナーがおすすめの職業である理由として挙げられる、
・健康意識の高まりにより市場規模は拡大傾向
・多種多様な働き方が認められている
・年齢を重ねても働くことができる
の3点について以下で詳しく説明します。
健康意識の高まりになどより市場規模は拡大傾向
前述のとおり、
・今後の超高齢化社会の到来
・人々の健康意識の高まり
・ダイエットブーム
・人生100年時代に向けての健康維持
などによりスポーツジムの市場規模は拡大傾向であると考えられています。
以上のような時代的な背景から、スポーツトレーナーの需要は今後も増える見込みがあるため、スポーツトレーナーはおすすめの職業であるといえます。
多種多様な働き方が認められている
スポーツトレーナーは、多種多様な働き方が認められていることもおすすめの理由として挙げられます。
スポーツトレーナーはスポーツジムで社員として働くほか、フリーランスや独立開業してジムの経営をするなどの働き方もあります。
また、最近ではスポーツジムでは働かず、ネット上でオンライントレーナーとして働くスポーツトレーナーも多くなってきました。
様々な働き方ができることは、ライフスタイルの変化に合わせて快適な働き方を選べるということです。
結婚や育児などでライフスタイルが変わりやすい女性には、特におすすめといえるかもしれません。
年齢を重ねても働くことができる
前述のとおり、スポーツトレーナーは年齢を重ねても働くことができる職業の1つであるため、おすすめの職業です。
高齢になっても必要とされながら働けるように、経験による高いスキルや知識を今から積極的にコツコツと身に付けるようにするといいでしょう。
また、将来的にジムの経営を目指すなら、マーケティングスキルなども勉強しておくことをおすすめします。
スポーツトレーナーを目指す方におすすめの資格とは?
スポーツトレーナーになるのに必須の資格はありませんが、お客様の身体に責任を持ち、安全に指導するためにトレーナーの民間資格を取得しておくことを強くおすすめします。
また、資格を取得することでお客様からの信頼を得たり、就職や転職が有利になったりすることも期待できるでしょう。
本項では、スポーツトレーナーを目指す方におすすめの認知度の高い資格である、
・NSCA-CPT
・NESTA-PFT
の2つの資格について、以下で詳しく説明します。
NSCA-CPT
NSCA-CPTは、スポーツトレーナーを目指す人に非常におすすめの資格です。
NSCA-CPTは、NSCAジャパンが認定する国際的認知度が高い資格で、プロのアスリートから一般人まで幅広い層の対象者にトレーニング指導をするスキルや身体作り・筋力アップなどに関する専門的知識があることを証明します。
取得するためには、
・トレーニング・エクササイズの正しい知識
・プログラムプランニングのスキル
・解剖学・運動生理学・栄養学の知識
・安全性や法的な問題への理解
などが必要です。
NSCA-CPTの資格認定を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
1.NSCAジャパン会員である
2.満18歳以上
3.高等学校卒業者または高等学校卒業程度認定試験(旧:大学入学検定試験)合格者
4.有効なCPR/AEDの認定者
※引用元:https://www.nsca-japan.or.jp/exam/certification/requirements.html
同資格について詳しく知りたい方は、「NSCA-CPTとはどんな資格?受験条件・勉強法・活用方法を解説」をご覧ください。
NESTA-PFT
NESTA-PFTはアメリカのNESTAが発行する資格で、お客様のバックグランドや目標に適したトレーニングプログラムを提供できる知識があることを証明します。
NESTA-PFTは、スポーツトレーナーやインストラクターが取得しているスポーツ業界で最も有名な資格の1つとして知られています。
日本国内でも多くの人がNESTA-PFTを取得していますが、実務経験や養成講座、養成コースの受講が必要になるなど認定試験を受ける条件が厳しいことから、NESTA-PFTではなく、講習を受けなくても認定試験を受けられるNSCA-CPTを選んで取得する人もいます。
NESTA-PFTの資格認定を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
- NESTA JAPANもしくは医学映像教育センターからPFTのテキストを購入している
- CPR・AEDの技能を習得し、定期的にトレーニングを積んでいる
- 日本国籍または、日本での就労可能な在留資格がある
- 満18歳以上で、高等学校を卒業しているか高等学校卒業程度認定資格試験に合格している、またはNESTAが認定する教育カリキュラムのを修了している
該当要件として次のA~Dのうち1つ以上に該当する必要があります。
- 1年以上のパーソナルトレーナー・インストラクターなどの実務経験がある
- 1年以上の運動部指導、フィットネス企業勤務経験がある
- 体育系または、医療系の大学・専門学校を卒業している
- NESTAの認定する養成講座、養成コースを受講済みである
※引用元:https://www.nesta-gfj.com/pft
同資格について詳しく知りたい方は、「NESTA-PFT(ネスタ)とはどんな資格?取得までの手順と取得後の働き方を解説」をご覧ください。
トレーナーエージェンシーでは、
・トレーナーとして必要な素養
・具体的なトレーナーの働き方
・おすすめの資格
・トレーナー資格試験の力試し模擬問題
・うまく行く人/いかない人の違い
などをまとめた「【完全版】未経験からトレーナーになるための攻略ガイドブック」を”無料でプレゼント“しております。(内容の一部を先んじて見せちゃいます!)
下記ボタンからダウンロードできますので、ぜひご確認いただいた上で、ご自身の学習にお役立てください。
まとめ
今回の記事では、スポーツトレーナーに向いている人の特徴や「スポーツトレーナーはやめとけ」と言われている理由、スポーツトレーナーを目指す方におすすめの資格などについて説明してきました。
この記事を読んで、ご自身がスポーツトレーナーに向いているのかや、スポーツトレーナーはやめておけというのが誤解であることなどを確認していただけたら幸いです。
スポーツトレーナーの市場は、今後も拡大傾向にあります。スポーツが好きでスポーツ業界で働きたいという人は、パーソナルトレーナーのようなスポーツトレーナーを目指すのがおすすめです。
スポーツトレーナーを目指すなら、最初の一歩としてトレーナーの民間資格を取得することを考えましょう。資格を取得することで、今後スポーツトレーナーとして活躍する可能性を最大限高めることができます。
トレーナーエージェンシーでは、トレーナーを志す方向けに認定資格『NSCA』の完全攻略ガイドをお配りしています。興味のある方は、ぜひダウンロードしてみてください。