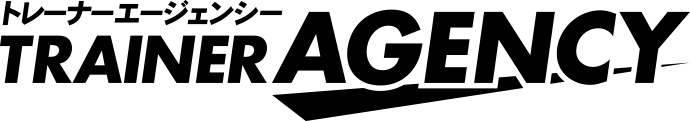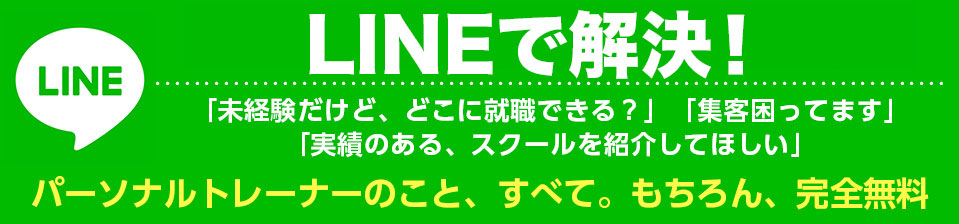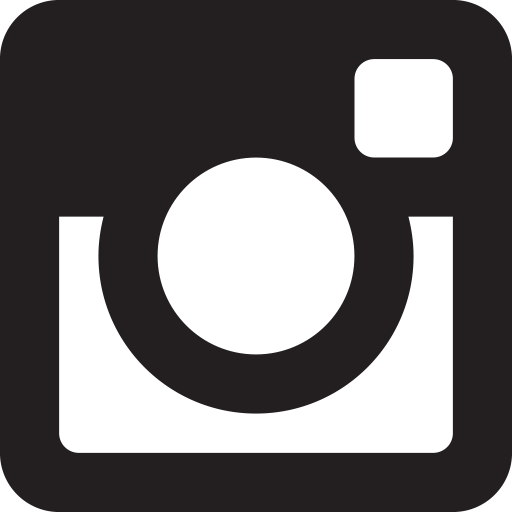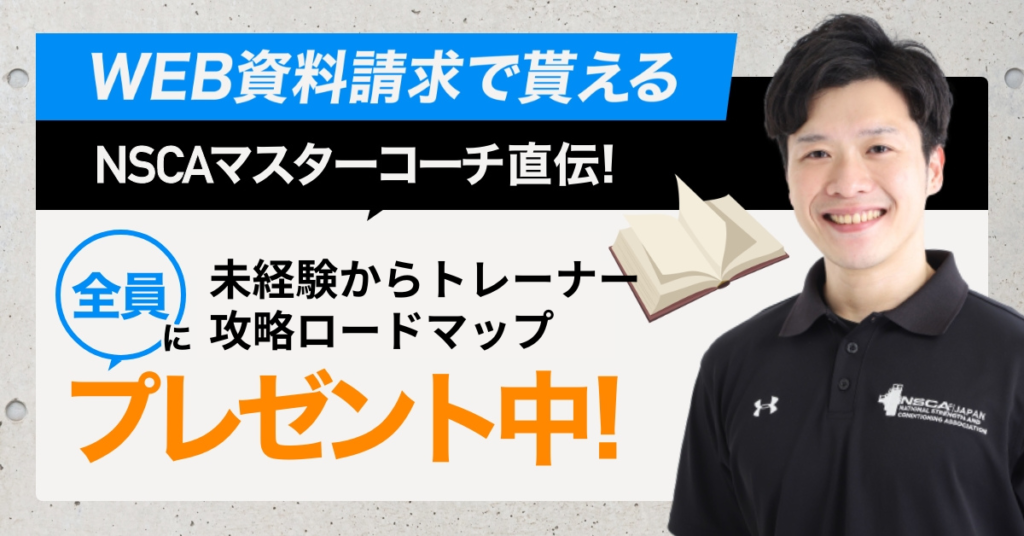スポーツ医療分野の資格を活かせる仕事は?資格の種類や勉強法も紹介!
 この記事では、スポーツ医療分野に関連する資格や資格を活かせる仕事、資格を取得するメリット、選び方、おすすめの勉強方法などについて網羅的に解説しています。
この記事では、スポーツ医療分野に関連する資格や資格を活かせる仕事、資格を取得するメリット、選び方、おすすめの勉強方法などについて網羅的に解説しています。
スポーツ医療分野には、さまざまな専門職が存在します。スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるためのトレーナーやけがからの回復をサポートする理学療法士など幅広い職種が活躍しています。
フィットネスクラブやリハビリ施設での指導はもちろん、アスリートのメンタルケアや栄養管理を担当する職もあり、どれも健康維持やパフォーマンス向上を目的とした仕事です。最近では、シニア層の健康維持やボディメイクをサポートする役割も注目されています。
これらの仕事で必要となる知識やスキルを身に付けるため、資格取得は大きなステップです。例えば、トレーナーやリハビリ専門職には、解剖学や運動生理学、心理学などの専門知識が求められます。資格を取得することで、こうした専門的な知識やスキルを体系的に学び、現場での信頼性を高めることができます。
この記事では、スポーツ医療分野で活躍できる仕事や関連する資格、資格の選び方、おすすめの勉強法などについて詳しくご紹介します。
スポーツ・医療分野で活躍できる仕事とは?
スポーツ・医療分野で活躍できる仕事には多くの種類があります。ここではスポーツ・医療分野の仕事の、
・スポーツトレーナー
・アスレティックトレーナー
・パーソナルトレーナー
・理学療法士
・整形外科医
以上の5つについて、以下で詳しく解説します。
スポーツトレーナー
スポーツトレーナーは、アスリートや一般のスポーツ愛好者に対して、身体能力の向上や怪我の予防、リハビリテーション支援などを行う専門職です。多くはスポーツチームやフィットネスジムなどで働き、トレーニングプログラムの作成や実技指導を担当します。
スポーツトレーナーとして活躍するには、運動生理学や栄養学、解剖学などの知識が求められ、関連資格を持つことが就職や信頼の向上に役立ちます。また、パーソナルケアの重要性が高まる中で、個別対応のスキルが重要視されています。
スポーツトレーナーは、スポーツパフォーマンスの最大化や安全管理を通じて、アスリートの目標達成を支える役割を担っています。
アスレティックトレーナー
アスレティックトレーナーは、スポーツ医学やリハビリの専門家として、主にプロのアスリートやスポーツチームを対象に活動する職業です。怪我の予防、応急処置、リハビリプランの作成、さらには競技復帰までのサポートを行い、選手の健康と安全を守るための重要な役割を担っています。
日本スポーツ協会が認定するアスレティックトレーナー資格(JSPO-AT)や、アメリカのNATA-ATC資格を取得することで、スポーツ現場での信頼性が高まります。
アスレティックトレーナーは、スポーツチームや医療機関、大学、さらにはプロスポーツの現場でも活躍し、専門的なトレーニングやリハビリの知識を提供し、選手の長期的な健康管理に貢献しています。
パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナーは、お客様一人ひとりに合わせたトレーニング指導を行う専門職で、体力向上やダイエット、ボディメイクのサポートを提供します。
多くのパーソナルトレーナーは、フィットネスジム勤務や独立開業の形で活動し、トレーニングプログラムをオーダーメイドで設計し、目標達成を支援します。また、解剖学や栄養学、トレーニング理論などの専門知識を活かし、安全で効果的な指導を行います。
パーソナルトレーナー関連の資格を取得することで、指導スキルの証明や信頼向上につながり、独立やフリーランス活動にも役立ちます。
パーソナルトレーナーは、個々の目標やニーズに合わせた指導で、健康や体力の向上に寄与する重要な存在です。
理学療法士
理学療法士は、医療機関やリハビリ施設で身体の機能回復を支援する専門家で、スポーツ医療の分野でも重要な役割を担います。
筋肉や関節の機能改善を目指し、個々の患者に合わせた運動療法や徒手療法を行い、スポーツ障害や怪我からの早期回復を図ります。スポーツに関わる理学療法士は、アスリートやスポーツ愛好者が安全にトレーニングを続けられるようサポートすることが求められます。
資格は国家資格であり、病院やスポーツクリニック、トレーニング施設など幅広い場で活躍することができます。
理学療法士は、医療とスポーツの両方で健康維持や機能改善を支える重要な存在です。
整形外科医
整形外科医は、骨や関節、筋肉など運動器の疾患や怪我の治療を専門とする医師で、スポーツ分野でも重要な役割を果たします。
スポーツによる怪我や障害の診断・治療、さらには手術やリハビリ計画の策定を行い、アスリートが安全に競技に復帰できるようサポートします。また、アスリートに特化した診療や予防ケアを提供することで、競技生活の質を向上させることが可能です。
整形外科医になるには医師免許が必要で、さらにスポーツ医学の専門知識を深めるために特別な研修を受けることも多いです。
トレーナーエージェンシーでは、
・トレーナーとして必要な素養
・具体的なトレーナーの働き方
・おすすめの資格
・トレーナー資格試験の力試し模擬問題
・うまく行く人/いかない人の違い
などをまとめた「【完全版】未経験からトレーナーになるための攻略ガイドブック」を”無料でプレゼント“しております。(内容の一部を先んじて見せちゃいます!)
下記ボタンからダウンロードできますので、ぜひご確認いただいた上で、ご自身の学習にお役立てください。
スポーツ医療分野に関する国家資格
スポーツ医療分野に関する資格はどのようなものがあるのでしょうか。本稿では、スポーツ医療関連の仕事で役立つ国家資格の、
・理学療法士
・あん摩マッサージ指圧師
・柔道整復師
・鍼灸師
・管理栄養士
・NATA-ATC
以上の6つについて以下で詳しく解説します。
理学療法士
理学療法士は、リハビリテーション専門の国家資格で、怪我や病気で身体機能が低下した人をサポートし、日常生活やスポーツへの復帰を促進する役割を担います。
医療機関やリハビリ施設、スポーツチームで活動し、運動療法や物理療法を用いて患者の回復を支援します。スポーツ分野では、アスリートのリハビリテーションや体力の維持向上にも貢献し、怪我予防のトレーニング指導も行います。
理学療法士になるには、専門学校や大学で3年以上の医療系のカリキュラムを修了し、国家試験に合格する必要があります。
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧師は、指圧やマッサージの技術を用いて筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、身体の痛みや疲労を緩和する専門職の国家資格です。
スポーツ分野では、アスリートの筋肉の調整や疲労回復をサポートし、怪我の予防やパフォーマンスの向上に貢献します。特に試合前後のケアやコンディション調整のために重要な役割を果たします。
あん摩マッサージ指圧師の資格を取得するためには、大学や専門学校で3年以上学んだ後、国家試験に合格することが必要です。
柔道整復師
柔道整復師は、捻挫や骨折、脱臼といった外傷の治療を行う専門職であり、特にスポーツ選手の怪我のケアやリハビリにおいて重要な役割を担っています。
柔道整復師は整骨院や接骨院での施術だけでなく、スポーツチームに専属トレーナーとして携わったり、アスリートと密接に関わりながら活動することも多いです。
スポーツの現場では、怪我の治療だけでなく、怪我を予防するためのアドバイスやリハビリプランの作成などにも活かされ、選手のパフォーマンスを最大限にサポートします。
資格を取得するためには、認可を受けた専門学校や大学で3年以上のカリキュラムを修了した後、国家試験に合格する必要があります。
鍼灸師
鍼灸師は、鍼(はり)や灸(きゅう)を用いてツボを刺激し、体の不調を整える伝統的な医療技術の国家資格です。
スポーツ医療の分野においても、鍼灸師はアスリートのコンディション調整や疲労回復、怪我のリハビリテーションに貢献しています。例えば、筋肉の張りや関節の痛みを和らげることで、パフォーマンスを向上させるだけでなく、怪我の予防にも役立つため、スポーツ現場での需要が高まっています。
鍼灸は、体内のエネルギー(気)の流れを調整し、自然治癒力を高めることを目的とするため、西洋医学とは異なるアプローチを取ります。そのため、鍼灸師は解剖学や生理学、経絡(けいらく)などの専門知識を持ち、選手一人ひとりの体調に合わせたケアを行います。また、ストレスやメンタルケアにも効果があるとされており、競技生活の中で心身の健康を維持するサポート役としても活躍しています。
鍼灸師になるためには、認可を受けた大学・専門学校で3年以上学び、国家試験に合格する必要があります。
管理栄養士
管理栄養士は、健康や栄養に関する専門的な知識を活かして、栄養管理や健康維持をサポートする国家資格です。
特にスポーツ医療の分野においては、アスリートのパフォーマンスを最適化するための食事管理や栄養指導を行います。アスリートは日々のトレーニングの効果を最大限に引き出し、また試合に向けて体力を維持し、怪我のリスクを減らすためにも適切な栄養管理が求められます。そのため、管理栄養士はアスリートに合わせた食事プランを提供し、必要な栄養素を効果的に摂取できるようサポートします。
管理栄養士になるためには、認定された大学や専門学校で栄養学を修め、国家試験に合格することが必要です。
NATA-ATC
NATA-ATCは今まで紹介した日本の国家資格とは異なり、アメリカの国家資格になります。NATA(National Athletic Trainers’ Association:全米アスレティックトレーナー協会)が認定する資格で、アメリカでは95%のスポーツトレーナーがこの資格を取得しており、スポーツ現場で活動するには必須の資格です。
NATA-ATCを取得することで、アスリートのケガ予防、応急処置、リハビリテーション、そしてパフォーマンス向上に関わる専門的なトレーニング方法など、多岐にわたるスキルが身に付きます。また、アメリカ国内のスポーツイベントやプロチームで働く際には、この資格が必須とされ、公式に活動するためには取得が不可欠です。
NATA-ATCを取得するためには、アメリカの大学・大学院に留学し、アスレティックトレーナー養成のカリキュラムを終えること、卒業までに700〜800時間のインターンシップを終えること、3種類の試験に合格することが必要です。
スポーツ医療分野に関する民間資格
前項ではスポーツ医療分野の仕事で役立つ国家資格を紹介しました。
ここでは、民間資格の
・JSPO-AT
・JATI-ATI(日本トレーニング指導者協会認定資格)
・NSCA-CPT(NSCA認定パーソナルトレーナー)
・健康運動指導士
・スポーツメンタルトレーニング指導士
以上の5つについて以下で詳しく解説します。
JSPO-AT
JSPO-ATは、日本スポーツ協会が認定する民間資格で、日本国内におけるアスレティックトレーナー資格の中でもトップレベルとされています。
この資格を取得することで、スポーツ医学や運動生理学、また選手の怪我予防、リハビリ、コンディショニングに必要な専門知識と技術を持っていることを証明でき、スポーツ現場での信頼度が向上します。
JSPO-ATを取得するためのプロセスは、大きく以下の2段階に分かれています。
・養成講習会を受講する、または免除適応コース承認校を卒業すること
・筆記試験および実技試験の2つで構成された検定試験に合格すること
試験の合格率は非公表ですが、筆記試験については、日本スポーツ協会の養成講習会を修了した場合で約30-40%、免除適応コース承認校を卒業した場合は約10%程度とされています。実技試験に関しては、合格率は約70%と見込まれています。
資格取得に必要な費用は以下の通りです。
養成講習会受講料:
共通科目 22,000円+リファレンスブック代(電子版2,640円または紙版3,300円)
専門科目 55,000円+テキスト代(電子版8,910円または紙版11,000円)
資格登録料:4年間で20,000円
受験料:
筆記試験 16,500円
実技試験 33,000円
JATI-ATI(日本トレーニング指導者協会認定資格)
JATI-ATIは、日本トレーニング指導者協会が認定する民間資格であり、アスレティックトレーナーとしてのスキルを証明するための資格です。
この資格を取得することで、筋力トレーニングや体力向上、コンディショニングに関する理論や実技を幅広く学ぶことができ、スポーツ科学に基づいた効果的なトレーニング指導が可能になります。特に科学的根拠に基づいた指導法を提供できる点がJATI-ATIの大きな特徴です。
JATI-ATIの認定試験を受験するには、まずJATIへの入会が必須で、その後、養成講習会の受講と自己学習課題(ワークシート)の提出が求められます。
さらに、講習会の受講資格として以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。
・4年制大学卒業者(卒業見込み含む)
・短期大学や専門学校卒業者(卒業見込み含む)
・職業能力開発大学校の専門課程修了者(修了見込み含む)
・各省の大学校(防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など)修了者(修了見込み含む)
・高卒以上で3年以上の運動指導歴がある方
また、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)や健康運動実践指導者、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師などの資格保持者は、一般科目の講習および課題の提出が免除されるメリットもあります。
試験の合格率はある程度変動しますが、一般対象者の合格率は約80-90%、養成校・機関対象者は約50-70%とされています。
資格取得には、日本トレーニング指導者協会の年会費11,000円、講習会受講料115,500円、検定試験受験料33,000円が必要で、合計で159,500円の費用がかかります。
NSCA-CPT(NSCA認定パーソナルトレーナー)
NSCA-CPTは、NSCA(全米ストレングス&コンディショニング協会)によって認定されるパーソナルトレーナー資格であり、科学的根拠に基づくトレーニング指導を学びたい人におすすめの資格です。
この資格を取得すると、トレーニングプログラムの立案や筋力トレーニング、体力向上に関する高度なスキルを身につけることができます。加えて、解剖学や生理学、リハビリテーションの分野も含まれているため、トレーナーに求められる幅広い知識と技術が得られます。
NSCA-CPTを取得するには、次の条件を満たす必要があります。
・NSCAジャパンの会員であること
・満18歳以上であること
・高校卒業または同等の資格を持っていること
・有効なCPR/AEDの資格を保有していること
これらの条件をクリアした後、NSCA-CPT認定試験に合格することが求められます。
試験の合格率は約80%で、受験料は46,090円です。
NSCA-CPTはスポーツジムやフィットネスクラブで高い評価を得ており、トレーナーとしての就職活動で有利に働く資格としても知られています。
健康運動指導士
健康運動指導士は、健康・体力づくり事業財団が認定する資格であり、健康促進や生活習慣病予防に役立つ運動指導を専門的に学ぶための資格です。
この資格を取得すると、健康管理や生活習慣病予防を目的とした運動指導が可能になり、医療機関やフィットネスクラブ、公共施設における信頼性が高まります。専門的な知識を習得することで、幅広い年齢層に対し、安全で効果的な運動プログラムを提供できるため、予防医療の観点から運動指導を行いたい方にとって最適な資格です。
健康運動指導士の資格を得るためには、次の条件を満たす必要があります。
・健康・体力づくり事業財団の養成講習会を受講する、または健康運動指導士養成校を修了すること
・認定試験に合格すること
養成講習会の費用は選択するコースにより異なり、教材費込みで133,650円から288,750円です。また、認定試験の受験料は13,619円です。
スポーツメンタルトレーニング指導士
スポーツメンタルトレーニング指導士は、日本スポーツ心理学会が認定する資格で、アスリートのメンタルサポートや心理的なトレーニングに関する専門的な指導を行う資格です。
この資格を取得することで、スポーツ心理学やメンタルトレーニングに関する高度な知識と技術を身につけ、選手のメンタルパフォーマンスを向上させるサポートが可能になります。特に、メンタル面の安定を求められる競技スポーツにおいて、スポーツメンタルトレーニング指導士は重要な役割を果たします。
資格取得のための条件は以下の通りです。
・日本スポーツ心理学会に加入し、2年間の在籍期間があること
・大学院でスポーツ心理学または関連領域を専攻し、修士号を取得すること
・論文執筆などで学術成績を日本スポーツ心理学会が定めた基準で5点以上持っていること
・研修会参加などの研究実績で日本スポーツ心理学会が定めた基準で10点以上持っていること
・直近5年間で30時間以上、スポーツ現場で心理的指導の実績があること
これらの条件をクリアしたうえで、指導士資格取得講習会を受講して課題を提出し、最終審査に合格する必要があります。
スポーツ医療資格の選び方のポイント
前項まででスポーツ医療に関する資格を紹介しましたが、種類が多くどの資格を取得すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、取得する資格を選ぶ上でのポイントの、
・自分の目指すキャリアに合っているか
・資格の難易度
・取得までの学習期間
・取得にかかる費用
以上の4つについて、以下で詳しく解説します。
自分の目指すキャリアに合っているか
スポーツ医療分野の資格を選ぶ際には、まず自分が目指すキャリアに合致しているかを確認することが大切です。
例えば、アスリートのリハビリやケガの予防に携わりたい場合は、リハビリテーションや体の構造に関する専門知識が求められる理学療法士やアスレティックトレーナーといった資格が適しています。一方、トレーニングプランを作成したり、体力向上のサポートを行いたいのであれば、パーソナルトレーナーに関連する資格が良いでしょう。また、栄養管理やメンタルサポートなどに興味があるなら、管理栄養士やスポーツメンタルトレーニング指導士などの資格が役立ちます。
資格選びの際は、自分のキャリア目標と照らし合わせ、必要な専門知識やスキルが身に付く資格を選ぶことが成功のポイントです。
資格の難易度
資格の難易度は、取得のハードルや試験の内容によって大きく異なります。
例えば、国家資格やJSPO-ATなどは難易度が高く、学習期間も長期にわたり、試験内容も専門的です。これらの資格を取得するには、医学的な知識や実技のスキルが求められ、さらに実習や研修を経ることが一般的です。難易度が高い資格を取得することで、トレーナーや医療分野の専門家としての信頼を高め、実力を示すことが可能になります。
反対に、難易度が比較的低い資格であれば、短期間で取得できるため基礎的な知識を身に付けるのに適しています。
資格の難易度を考慮し、自身のキャリアや学習計画に合ったものを選ぶことが重要です。
取得までの学習期間
資格取得には学習期間も影響します。短期間で取得できる資格もあれば、数年にわたる学習や実習が必要な資格もあります。
例えば、国家資格である理学療法士や柔道整復師などは、数年の学習と実習が必要で、大学や専門学校への通学が必須です。一方、パーソナルトレーニング民間資格などであれば数ヶ月で取得可能なものもあり、働きながらでも学べるカリキュラムが組まれていることが多いです。
自身のスケジュールや現在の状況に応じて、学習期間を考慮した資格を選ぶことが大切です。無理のない範囲で学習を進められる資格であるかを確認しましょう。
取得にかかる費用
資格の取得費用も慎重に考えるべき要素です。
資格によっては数万円の受験料程度で済むものもあれば、数十万円から百万円以上の費用がかかるものもあります。特に大学や専門学校への通学が必要な資格は、学費が高額になりがちです。
一方で、比較的費用を抑えられるオンライン講座や独学で取得可能な資格もあります。また、必要な教材や受験料、更新料などの追加費用も含めて総額を考慮しましょう。
将来的な収入やキャリアアップを見越して、自己投資としてどれだけの費用をかけることができるかを見極め、自分にとって負担にならない範囲で資格を選ぶことが望ましいです。
スポーツ医療分野の資格を取得するメリット
ここまではスポーツ医療分野の資格の種類や選び方について解説してきました。本稿では、スポーツ医療分野の資格を取得するメリットを紹介します。
具体的なメリットは、
・専門的な知識やスキルを身に付けられる
・アスリートやお客様から信頼を得られる
・就職の際に有利になる
・独立する際のブランディングになる
以上の4つです。以下でそれぞれ詳しく解説します。
専門的な知識やスキルを身に付けられる
スポーツ医療分野の資格を取得することで、専門的な知識や技術を体系的に身につけることができます。
資格を取得することで身に付けられる知識には、解剖学や生理学、トレーニング理論、リハビリテーションなど、スポーツにおける医療的な基礎知識が含まれるため、科学的根拠に基づいた指導が可能となります。さらに、現場での実習やインターンシップが組み込まれた資格も多く、実践的なスキルも学べるため、選手や患者のケガ予防やパフォーマンス向上に直接役立てることができます。
このようなスキルは、競技の現場や医療施設で即戦力として活躍する上で重要であり、資格を取得することで他の指導者との差別化を図れるため、非常に大きなメリットとなります。
アスリートやお客様から信頼を得られる
スポーツ医療分野の資格を持つことは、アスリートやお客様からの信頼を得るための大きな強みとなります。
専門的な知識や技術を習得していることを証明できるため、怪我の予防やリハビリ、パフォーマンス向上といった場面で、アスリートやお客様に対して安心感を与えることが可能です。特に、ケガや体調管理に対する不安を持つアスリートやお客様にとって、資格保有者のサポートは信頼性が高く、より効果的で安全なアドバイスやトレーニング指導を受けられると感じることが多いでしょう。
また、資格を持っていることで、より高い技術と知識を提供できるプロフェッショナルとして認識され、他の指導者との差別化を図ることが可能です。資格取得はアスリートやお客様に対する責任感や信頼を強化するだけでなく、自身のキャリアにおいても価値のある資産となります。
就職の際に有利になる
スポーツ医療分野の資格を持っていることは、就職や転職の際に大きな強みとなります。
特にフィットネスクラブや医療機関、リハビリ施設、スポーツチームなどでは、専門知識を持つ人材が求められるため、資格を有することで、就職活動で有利になることが多いです。また、資格保持者は一定の教育や実習を経ており、信頼性が高いと評価されやすい点もポイントです。
資格によっては、特定の業務を担当できる独占的な業務範囲が決まっているものもあり、スポーツ医療の資格を取得することで、業務の幅を広げ、キャリアの選択肢を増やすことができます。
独立する際のブランディングになる
スポーツ医療分野の資格は、独立やフリーランスでの活動を支援する強力なブランディングツールとなります。
資格を持つことで、専門的な知識と技術を有していることを証明でき、信頼性の高いプロフェッショナルとしての認知が広がります。例えば、パーソナルトレーナーやアスレティックトレーナーとして独立する場合、資格があることで顧客からの信頼を得やすく、集客やリピート率向上にもつながるでしょう。
また、資格取得に伴い、ネットワークや情報提供を受けることもできるため、業界内での人脈形成にも役立ちます。
スポーツ医療資格の勉強方法
続いて、スポーツ医療資格の勉強方法を解説します。具体的な勉強方法は、
・独学で学ぶ
・大学・専門学校に通う
・パーソナルトレーナー養成スクールに通う
以上の3つです。以下で詳しく解説します。
独学で学ぶ
独学でスポーツ医療資格を目指す方法は、費用を抑えつつ自分のペースで学習を進められる点がメリットです。
書籍やオンライン教材を利用して、大学や専門学校に通う必要のない民間資格に必要な基礎知識を学ぶことができます。柔軟なスケジュール管理が可能なため、仕事や他の活動と並行して資格取得を目指したい方に適しています。
ただし、独学の場合、わからない部分を質問する機会が限られるため、自己解決能力が求められます。また、実技スキルを要する資格の場合、実習が不足しがちな点もデメリットです。
独学は、自己管理が得意で、時間をかけて資格取得を目指したい方におすすめです。
大学・専門学校に通う
大学や専門学校では、資格の取得に必要な知識やスキルを体系的に深く学ぶことが可能です。特に、理学療法士や作業療法士、柔道整復師といった国家資格を目指す場合、専門的な学習環境が整った大学や専門学校に通うのが必須です。
大学・専門学校では、資格取得に必要なトレーニング理論や解剖学、生理学、栄養学といった専門知識を基礎から学べるカリキュラムが用意されています。さらに、実技演習やインターンシップの機会もあり、現場で役立つ実践的なスキルを養える点も大きな魅力です。
一方で、デメリットとして挙げられるのは、学費の高さや卒業までにかかる時間です。大学や専門学校では、通常、学費が2〜300万円かかり、加えて教材費や施設使用料などの負担も生じます。費用が大きい点は注意が必要です。
また、通学期間としては、大学なら4年、専門学校でも2〜3年かかるため、卒業までに時間がかかることも考慮する必要があります。
パーソナルトレーナー養成スクールに通う
NSCA-CPTなどのパーソナルトレーナー関係の資格を取得したい場合は、パーソナルトレーナー養成スクールに通うこともおすすめの勉強方法です。
パーソナルトレーナー養成スクールは、パーソナルトレーナーとして必要な知識やスキルを短期間で学べる専門教育機関です。スクールの特徴は、資格取得に必要な内容を効率的に習得できる点にあり、短期間で集中して学びたい方に向いています。
養成スクールでは、解剖学やトレーニング理論などの基礎知識から、実際のトレーニング指導やお客様への対応方法といった、実務に直接つながるスキルまで身につけることができます。特に実技を重視したカリキュラムが多く、現場で即戦力となるための技術を習得できるのが強みです。
また、試験対策やサポート体制も充実しているため、初心者でも安心して学習を進めることができます。資格取得を目指し、効率よくスキルを身につけたい方には、パーソナルトレーナー養成スクールでの学習がおすすめです。
パーソナルトレーナー資格を取るならパーソナルトレーナー養成スクールがおすすめ
パーソナルトレーナー資格の取得を目指すなら、パーソナルトレーナー養成スクールに通うのがおすすめです。
独学では実技スキルをしっかりと習得するのが難しく、また大学や専門学校は学費が高額で、卒業までの期間も長いため、短期間での資格取得を目指す方には負担が大きくなりがちです。
一方、トレーナー養成スクールでは、実技に重きを置いたカリキュラムが組まれており、短期間で即戦力として活躍できるスキルが身に付きます。さらに、試験対策やサポート体制も整っているため、資格取得の成功率が高く、安心して学習に集中できます。
費用や学習時間のバランスが取れているため、未経験からパーソナルトレーナーを目指す方には、最適な学び方といえるでしょう。また、一部のスクールでは履歴書の添削や面接対策など、就職支援も行われており、キャリア形成のサポートも期待できます。
おすすめのトレーナー養成スクールはトレスク
トレーナー養成スクールは数多くありますが、特におすすめのスクールは「トレスク」です。トレスクでは、NSCA-CPTの資格取得を目指すことができます。
トレスクでは、未経験者でも短期間でNSCA-CPT合格を目指せるよう、万全のサポート体制が整えられています。
・単なる暗記ではなく、現場で役立つ実践的な知識やスキルを習得できる
・資格取得後もサポート体制が充実している
・認定講師によるわかりやすい授業が提供される
・短期間で効率よく学べるカリキュラム
このような特徴を備え、最短3か月でNSCA-CPTの合格を目指せるプログラムが用意されています。実際、NSCA-CPTの全体の合格率が約80%であるのに対し、トレスク卒業生の合格率は97.29%と非常に高い水準を誇ります。
さらに、トレスクは完全オンラインのスクールで、物理的な校舎を持たずすべての講座がオンラインで完結します。居住地に関わらず受講可能なため、誰でも気軽に学習を始められる点も魅力です。
トレーナーエージェンシーでは、
・トレーナーとして必要な素養
・具体的なトレーナーの働き方
・おすすめの資格
・トレーナー資格試験の力試し模擬問題
・うまく行く人/いかない人の違い
などをまとめた「【完全版】未経験からトレーナーになるための攻略ガイドブック」を”無料でプレゼント“しております。(内容の一部を先んじて見せちゃいます!)
下記ボタンからダウンロードできますので、ぜひご確認いただいた上で、ご自身の学習にお役立てください。
まとめ
スポーツ医療分野の資格を取得することで、アスリートの健康管理やトレーニング指導、リハビリテーションなど多岐にわたる活躍が可能です。
各種資格には専門的な知識やスキルが求められ、取得後は医療機関やフィットネス業界、またフリーランスとして独立する道も開かれています。資格の種類や勉強法を把握し、自分のキャリアに最も合った資格を選ぶことで、より効果的にスキルを活かせるでしょう。
それぞれの資格の特徴や必要な学習方法を理解し、将来のキャリアに向けてしっかりと準備を進めてください。スポーツ医療分野の知識を深めることで、社会貢献度の高い仕事にも挑戦できるはずです。
トレーナーエージェンシーでは、トレーナーを目指している方向けに認定資格『NSCA』の完全攻略ガイドをお配りしています。興味のある方は、ぜひダウンロードしてみてください。